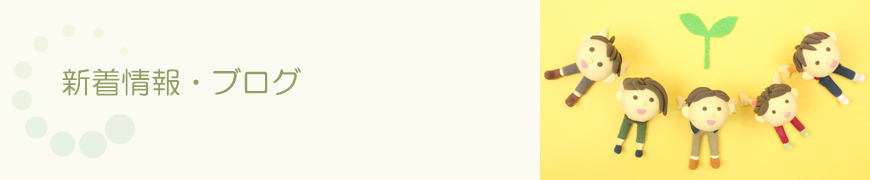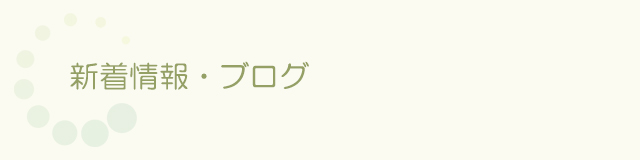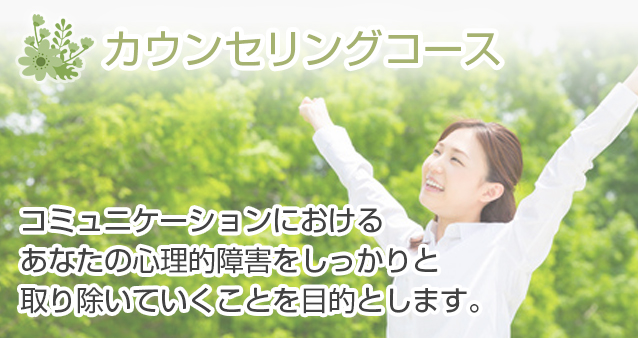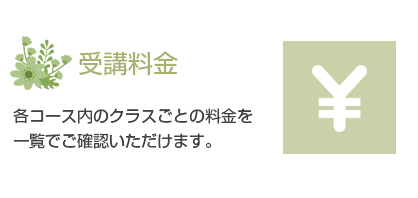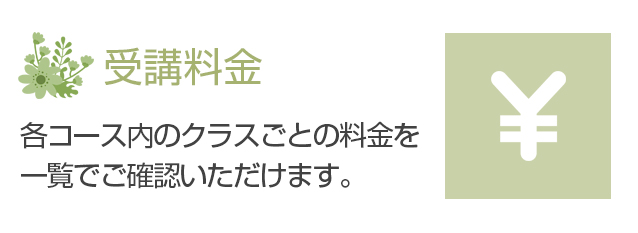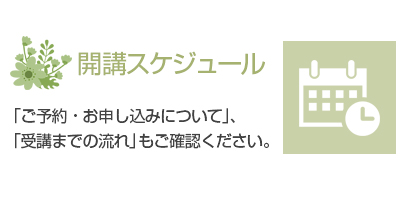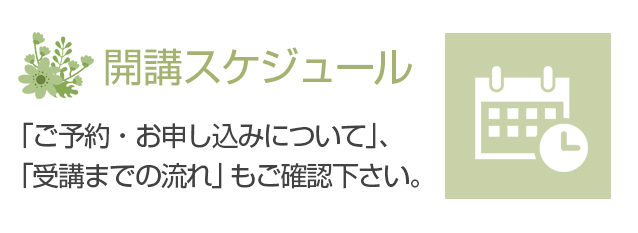-
- 2025.12.30相手の本音を自然と引き出す会話術
-
こんにちは!
今回は、話し方教室ネイチャースタイルで30年以上の指導経験からまとめた“相手の本音を自然と引き出す会話の技術”を紹介します。「相手が本音を話してくれない…」
「こちらが質問しても、表面的な返事しか返ってこない気がする」
でも、会話が苦手な人にとっては、「どう接したら相手が打ち解けてくれるか分からない」という声をよくいただきます。実は、本音を引き出すのに必要なのは“テクニック”よりも、相手が安心して話せる空気づくりです。これは心理カウンセリングでも、話し方レッスンでも共通しています。
相手が「この人になら話しても大丈夫だ」「否定されない」と感じる『安心感』を作ることが最も重要です。
無理に聞き出そうとせず、自然と相手が口を開きたくなるようなアプローチを、心理学的な観点も含めていくつか紹介します。1.ポジションと環境の工夫
本音を引き出すには、テクニックよりもまず「環境づくり」。
真正面に向き合うと「対立」の心理が働き、緊張感が高まります。💫おすすめの座り方:
・横並び(カウンター席やベンチ)や、L字型(90度の位置)に座る。
・同じ方向を見ることで「仲間意識」が生まれやすくなります。💫おすすめの位置:
・相手の右側(自分の顔の左側)に位置する。
・人の顔は左右対称ではありません。左側は“社会の顔”と言って、右と比べて穏やかで柔和な表情になっています。💫おすすめのシチュエーション:
・「ながら」会話:車の運転中、散歩中、食事中など、視線が合いすぎない状況。
・夜の時間帯:副交感神経が優位になり、リラックスして本音が出やすくなります。2.「質問」より先に“安心感”を渡す
相手が心の中でこう感じた時、本音は自然と出てきます。
・「この人なら否定しない」
・「話しても大丈夫だ」
・「理解しようとしてくれている」大切なのは、あなた自身が“安心できる人”であること。
3.まず自分から「弱み」を見せる(自己開示)
心理学には「返報性の原理」というものがあります。「相手がオープンにしてくれたから、自分もオープンにしよう」という心の働きです。
これは、相手が心を開いてくれる効果的な第一歩です!🟡たとえば…
いきなり「どう思ってる?」と聞くのではなく、「実は私、最近〇〇について自信がないんだよね」「正直、最初は不安だったんだ」と、自分の小さな本音や弱みを先にさらけ出します。
4.本音を引き出す会話スキル
୨୧┈┈┈┈1⃣┈受容の姿勢┈┈┈┈┈┈୨୧
💫ポイント:“安心させる相づち”で場を暖め、“否定を一切しない”
相づちの目的は「聴いていますよ」を伝えること。・「なるほど」
・「そうなんですね」
・「たしかに」💫ポイント:質問より“共感”を先に置くこと。
焦って質問すると、取り調べのようになり、本音が出にくくなります。・否定しない
・急かさない
・結論を急がないこれだけで、相手は驚くほど心を開いてくれます。
💫聞き方のコツ:
・たとえ反対意見でも、まずは「なるほど、そう思っているんだね」「そういう見方もあるね」と受け止めます。
・アドバイスや反論は、相手が全て出し切った後、求められた時だけにします。୨୧┈┈┈┈2⃣┈「なぜ?」を使わずに深掘りする┈┈┈┈┈┈୨୧
・「どう感じたの?」
・「その時どんな様子だった?」
・「もう少し教えてもらってもいい?」“状況”と“気持ち”をセットで聞くと、本音まで自然とたどり着けます。
୨୧┈┈┈┈3⃣┈相手の言葉を「少しだけ言い換えて返す」┈┈┈┈┈┈୨୧
🟡たとえば…
相手「最近、仕事がしんどくて…」
あなた「しんどい日が続いているんですね。どんな時に特にそう感じますか?」୨୧┈┈┈┈4⃣┈相手が答えやすい形式での質問テクニック┈┈┈┈┈┈୨୧
・数値化する:例)「今の状況、100点満点だと何点くらい?」
・第三者視点:「〇〇さんなら、なんて言うかな?」
・極端な質問:「一番最悪なケースって何だと思う?」
・他人も同様:他人の問題例を出して、「あなたは?」୨୧┈┈┈┈5⃣┈沈黙を恐れない┈┈┈┈┈┈୨୧
本音が出る前には、必ず“間”が生まれます。実はその沈黙こそが本音の入口。
沈黙が待てずに(怖くて)すぐ話を足そうとすると、相手が言いかけた本音が消えてしまうことがあります。
特に、情報処理がゆっくりめの方は 考える時間が必要。
「ゆっくりで大丈夫ですよ」という雰囲気を出すことで、本音が引き出しやすくなります。ネイチャースタイルのレッスンでも、受講生が考えている時はあえて待つことがあります。
すると、数秒後に「実は…」と本音が出てくることが多いのです。୨୧┈┈┈┈6⃣┈「もしも」の話でハードルを下げる┈┈┈┈┈┈୨୧
現実的な制約(予算、時間、立場など)があると、人は本音を隠しがちです。
「仮定の話」にすることで、責任を感じずに話しやすくなります。5.本音を引き出す会話のNG例
・「え、そう思うの?」とすぐ評価する
・「でもさ」と否定から入る
・解決策を先に提案する
・「ということは・・・」話を勝手にまとめる
・「だから、それで?」と急かす
・興味のない態度を見せる🧩まとめ
本音を引き出す会話は、特別な技術ではありません。
安心感 × 答えやすい質問 × ゆっくりした対話この3つがそろうと、相手は自然と心を開いてくれます。
ネイチャースタイルのレッスンでも、受講生の方が「こんなに話せると思わなかった」と驚かれることが多いのは、この“安心の会話”を大切にしているからです。
あなたの周りの大切な人とも、ぜひ試してみてくださいね。
受講生の声やインタビューも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
👉 受講者の声一覧
👉 話し方レッスン成果|受講生インタビュー次回も「話し方のコツ、ワンポイントレッスン」で、日常をもっと心地よくするヒントをお届けします✨
[吉国 裕子] 話し方教室 ネイチャースタイル / コミュニケーショントレーナー・心理カウンセラー
-
- 2025.11.29【診断テスト】話すのが怖い?心理的ブロック度チェックと克服法
-
その「話しにくさ」、実は心のブレーキかもしれません。
こんにちは! 話し方教室「ネイチャースタイル」講師であり、心理カウンセラーの視点から皆さんをサポートしている吉国です。人前で話すとき、
「言葉が出てこない」
「頭が真っ白になる」
「自分の声が小さくなる」
「相手の反応が気になる」そんな“話すことへの心理的なブロック”を感じる方は、とても多いです。
もしあなたもそう感じているなら、それはあなたの「能力の問題」ではありません。
「話すことへの心理的なブロック(心のブレーキ)」がかかっている「心の問題」かもしれません。今回は、あなたの心がどれくらいブレーキをかけているかを知るため、当教室のレッスンでも実際に使用している「話すことへの心理的ブロックの度合いをチェックする診断テスト」をご紹介します。
単なる不安チェックではなく、心理カウンセリング歴30年以上の視点とネイチャースタイル独自のレッスン経験をもとに作成しています。
まずは自分の現在地を知ることから始めましょう。それが克服の第一歩になります。✴️ 話すことへの心理的ブロック診断テスト
以下の10項目について、当てはまるものに ✔ を入れてみてください。
□ 1. 人前に立つと、動悸がして息苦しくなることがある
□ 2. 会話の前に「失敗したらどうしよう」「うまく話さなきゃ」と考えがち
□ 3. 過去に“話し方を指摘された一言”や人前で恥をかいた経験が忘れられない
□ 4. 初対面や人前で、声が急に小さくなる
□ 5.「どうせ自分の話なんて面白くない」と感じている
□ 6. 話している途中で「どう思われているだろう」など、相手の表情に過敏に反応してしまう
□ 7. 頭の中で文章を完璧に整理しないと話し出せない
□ 8. 話し終わった後に「もっと言えばよかった」「やっぱりダメだった」と落ち込む
□ 9. 会議や自己紹介の順番が近づくと、逃げ出したくなる
□10. 沈黙が怖くて、焦って余計なことを話してしまう・言葉が出ず、沈黙してしまう経験がある✳️ 診断結果の目安と傾向
▶ 0~3個:軽度
「話すこと」そのものより、場面による緊張が原因の方が多い状態です。
雑談や慣れた場では話せることが多いため、ちょっとしたコツや準備で改善しやすいタイプです。▶ 4~6個:中程度
「話す=緊張する行為」として脳に記憶されている状態。
自分で思っている以上に、心理的な負担が積み重なっていて、話そうとすると無意識にブレーキがかかり、実力の半分も出せていない状態です。
レッスンを始めると、「実は話し方よりも“心”が固まっていた」と気づく方が多い層です。
テクニックよりも、まずは「心の緊張」をほぐすことが先決です。▶ 7個以上:強度
過去の体験や環境による影響が大きく、“話すことの怖さ”が体に染みついている状態。
実際、当教室でもこの層の生徒さんは多く、「話すことが苦手ではなく“怖かっただけ”だった」と感じる方がほとんどです。
一人で悩まず、専門家と一緒に「なぜ怖いのか」を紐解く必要があります。🌠 ネイチャースタイル独自の視点:なぜ「心のブロック」は作られるのか?
一般的な話し方教室では、「大きな声を出しましょう」「滑舌を良くしましょう」と教わることが多いですね。もちろんそれも大切です。
しかし、私がカウンセラーとして、またネイチャースタイルの講師として多くの受講者様と接してきて確信していることがあります。心のブロックは、「他の人にとって“価値のある自分”であろうとするあまり生まれる」ということです。
当教室では多くの受講生が、こう話してくれます。
「話し方のテクニックだけでは改善しないと気づいた」
「気持ちをほどくと、急に話せるようになった」とくに、HSPさんや発達障害グレーゾーンの方は、「失敗できない」「相手に迷惑をかけたくない」
「叱られたくない」という思いが強く、小さな経験が大きなブロックにつながりやすい傾向があります。また、過去に受講された方には、“学生時代に笑われた一言”が30年近く心に刺さっていた…というケースもありました。
話す力は、テクニックより“心の可動域”が広がった瞬間に伸びる。
これは、長年のレッスンとカウンセリングの経験で確信していることです。受講生インタビューでもよく語られますが、「上手く話そうとするのをやめたら、逆に伝わるようになった」というパラドックス(逆説)こそが、ネイチャースタイルの神髄です。
🟡ネイチャースタイル受講生の実例:
ある受講生は、職場で説明を求められると涙が止まらなくなるほどの不安を抱えていました。
しかし、心理カウンセリングと話し方トレーニングを組み合わせることで、少しずつ「準備しなくても言葉が出てくる」状態へと変化しました【参考: 受講生インタビュー】。
このように、心理的なブロックは練習と心のケアで軽減できます。💖 心理的ブロックを外す「ワンポイント・カウンセリング」
💫 ブロック改善の第一歩は「自覚すること」
心理的なブロックは、“ある”ことに気づけた瞬間からゆっくり薄れていきます。
特に大切なのは、この3つです。①「怖い」と感じている自分を責めない
心理的ブロックを外す第一歩は、「緊張してもいい」と自分に許可を出すことです。
不安は自然な感情であり、怖さやドキドキは“性格”ではなく、脳があなたを守ろうとしている反応だからです。②「〜すべき」を「〜したい」に変換する
「失敗しないように話すべき」と考えると体が硬直します。
「この想いを伝えたい」「少しでも役に立ちたい」と、意識の矢印を「自分(守り)」から「相手(貢献)」に向けてみてください。③完璧な文章を話さなくてもいいと知る
ブロックが強いほど「完璧に話そう」とする傾向があります。まずは「不完全でも伝わればOK」と考えてみましょう。
実際、人は細かい話より“温度感”を聞いています。🧩最後に
“話すことへの心理的ブロック”は、特別な問題ではなく、誰にでも起こりうる自然な反応です。
そして、ブロックは「気づく → ほどく → 話せるようになる」という順番で確実に軽くなっていきます。まずは今回の診断で、ご自身の傾向を知ることから始めてみてください。
「心理的ブロック」は、長年の癖のようなものです。
一人で外すのが難しいときは、私を頼ってください。ネイチャースタイルでは、マニュアル通りの話し方を押し付けることはしません。
カウンセリング要素を取り入れたレッスンで、あなたの心が一番楽で、かつ相手に伝わる「あなたらしい話し方」を一緒に見つけ出します。受講生の声やインタビューも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
👉 受講者の声一覧
👉 話し方レッスン成果|受講生インタビュー次回も「話し方のコツ、ワンポイントレッスン」で、日常をもっと心地よくするヒントをお届けします✨
[吉国 裕子] 話し方教室 ネイチャースタイル / コミュニケーショントレーナー・心理カウンセラー
-
- 2025.11.23「中身がないと…」で黙る方へ。話す自信が湧く秘訣
-
「ちゃんとした内容を話さなきゃ・・・」「自分の話なんて必要ないかも・・・」
そう思えば思うほど、言葉が出てこなくなり、気づけば黙り込んでしまう。
受講生からのこのご相談、実はとても多いんです。
ネイチャースタイル代表の私、吉国が話し方と心理の両面から、この悩みを解消する「話す自信が湧く秘訣」をお伝えします。⁉️なぜ、あなたは話せないのか?
あなたが話せないのは、「話すスキルがない」からではありません。この背景には共通する“ある思い込み”があります。
心の奥底にある、「完璧主義」や「承認欲求」が原因となっているケースがほとんどです。1. 完璧主義の罠:「中身」のハードルが高すぎる
「中身のある話」とは何でしょうか?多くの受講者さんに共通しているのが、話す前に自分の中で100点の内容を作ろうとする癖です。
「失敗したくない」「つまらないと思われたくない」という気持ちが強すぎると、100点の話題以外は口に出せない、と脳が判断し、発言をストップさせてしまうのです。しかし、人は会話するとき、他人にそんな完成度を求めていません。
実際、当教室に長年通ってくださっている方の中にも、「中身の薄い話をしてはいけないと思っていた」「雑談なのに、結論や意味を求めてしまって苦しくなった」という声が多く寄せられます。2. 承認欲求と自己否定:「自分なんて」という思い込み“共有の思い込み”
「自分の話なんか興味あるかな」という悩みは、「話すこと」よりも「自分という存在の価値」と結びついています。
これは「話して成功すれば自分には価値がある」「話して失敗したら自分には価値がない」という、極端な考え方(二項対立思考)に陥っている証拠です。話す前から「必要ないかも」と自己否定でフタをしてしまっている状態です。✨ ネイチャースタイル独自の視点
当教室では、話の中身=特別な知識や面白い出来事ではないとお伝えしています。
「感情のシェア」こそが、相手の心に響き、共感を呼ぶコミュニケーションの基本です。🟡「役立つ情報」より「あなたの視点」を大切に
→ 事実や知識だけでなく、「自分はこう感じた」「こう考えた」を添えると、話にオリジナリティが生まれます。🟡聞き手は“完璧な答え”より“人柄”を求めている
→ あなたの話は「必要ない」どころか、相手に安心感や共感を与える大切な要素です。日常のちょっとした出来事や感じたことを話すだけで、聞き手は「その人らしさ」を感じ、親近感を持ちます。
💡ワンポイントレッスン:”話す自信が湧く秘訣”
秘訣 1:話す「目的」を「相手の反応」から「自己開示」へシフトする
話す目的を「相手を満足させること」から、「自分を知ってもらうこと」に変えましょう。
🟡たとえば…
・今日はこんなことをして、こんな気持ちになった
・実は最近、こういうことに悩んでいる
・この前こんな場面があって、こう思ったこういう話こそ、相手の興味を引きます。
相手の興味を測るのは、実は非常に難しいことです。受講生の中には、「自分の趣味の話なんて誰にも響かないと思っていたのに、思い切って話したら共通の話題ができて一気に距離が縮まった」という実例がいくつもあります。(👉 受講生インタビューより)🟡実例…
以前、極度に人前で話せない受講生の方がいました。「話す価値がない」と悩んでいたその方に、まずは「今日食べたランチの感想」を15秒だけ話すトレーニングを繰り返してもらいました。その結果、「中身はなくても、まずは声に出せば誰かは聞いてくれる」という成功体験が、自信の土台となりました。
秘訣 2:話す内容の「中身」を「感情」に切り替える
話すべき「中身」は、特別な情報でなくて良いのです。あなたの「感情」こそが、一番の「中身」です。
🟡たとえば…:感情+事実
・「雨が降って、少し憂鬱な気持ちになりました。そのせいで、帰宅後すぐに寝ちゃいましたよ。」
・「この新製品、正直ちょっと驚きました!前のモデルのほうが好きだったんですよね。」
・「昨日、散歩に行ったんです。寒かったですが気持ちよかったです。」
・「今日ちょっと忙しくて…少し疲れています。」事実 → 感想(気持ち) 立派な“中身”です。
受講者さんの中には、雑談が苦手だった方が「感じたことを一言添える」練習だけで、会話のキャッチボールが驚くほどスムーズになった例もあります。💖 カウンセラーからのメンタルアドバイス:あなたには話す「価値」がある
「黙ってしまう」背景には、自己否定の気持ちが隠れています。「自分には価値がない」→「自分の話は価値がない」という無意識の思い込みが、緊張や恐れを生み、さらに話せなくなる悪循環に。だからこそ、難しく考えすぎてしまうのです。
「中身のある話」なんて、いつでも、誰でもできるわけではありません。会話はキャッチボールです。すごい豪速球(完璧な話)を投げる必要はありません。まずは、あなたが投げやすい小さなボール(感情や短い感想)をポンと投げてみましょう。
「話すこと」と「あなたの価値」は、全く関係ありません。“あなたという存在がその場にいる”ことに価値があるのです。
あなたの体験や感じたことこそ、聞き手にとって価値ある“中身”なのです。ネイチャースタイルでは、その人のペースで「自分の言葉を素直に出せる」練習を一緒に行っています。
そこでおすすめなのは、“小さな成功体験”を積み重ねること。・まずは一言だけ話す
・短い体験談「今日あったこと+その時の気持ち」をシェアする
・相手の笑顔やうなずきを確認するこの繰り返しが「話してもいいんだ」という安心感につながり、自然と声が出るようになります。
🧩最後に
話し方教室ネイチャースタイルでは、受講生の皆さんが抱えるこの心理的な悩みに真摯に向き合い、発言の「質」ではなく「量」、そして「心」を重視した指導をしています。
受講生の声やインタビューも、ぜひ参考にしてみてくださいね。👉 受講者の声一覧
👉 話し方レッスン成果|受講生インタビュー次回も「話し方のコツ、ワンポイントレッスン」で、日常をもっと心地よくするヒントをお届けします✨
____________________________________________________________________________________________________
[吉国 裕子] 話し方教室 ネイチャースタイル/ コミュニケーショントレーナー・心理カウンセラー
-
- 2025.11.17「言葉足らずの原因は“思い込み”?伝わる話し方のコツ」
-
今回は、「自分の中だけで分かっていることを、相手も知っていると思い込んで話してしまう」というお悩みについてお話しします。
話し方教室ネイチャースタイルの講師であり、心理カウンセラーの吉国が、この「無意識の思い込み」を打ち破り、情報を確実に伝えるための具体的な技術と、心の持ち方についてお話しします。言葉足らずの背景にある“前提のズレ”
「ちゃんと話したのに、伝わっていない」「説明したつもりなのに、相手がポカンとしている」
🟡 “共有の思い込み”
そんな場面、誰でも一度は経験があると思います。
でも実は、これは“話し方の技術”だけの問題ではありません。
多くの場合、それは自分の中では話がつながっているのに、相手に必要な情報を言葉にしていないために起こります。
その背景には、「自分の中の情報は、相手にもあるはず」という“前提のズレ”が潜んでいることが多いのです。特に、発達障害(グレーゾーン含む)の特性を持つ方にとっては、「言ったつもり」や「分かっているだろう」という“省略”ではなく、そもそも無意識のうちに「相手も同じ情報を持っている」と思い込みやすい傾向があります。
🟡 実例:受講生インタビューより
これは、悪気でも不注意でもなく、認知(脳の情報処理)のスタイルの違い。
だからこそ、責めるのではなく、丁寧に“橋をかける”工夫が必要です。ある受講生さん(40代・女性)は、職場での報告がうまく伝わらず悩んでいました。
「私はちゃんと話してるのに、なんで“説明不足”って言われるんでしょう?」と。
レッスンで話を聞いてみると、・報告の背景や目的が抜けている
・専門用語が前提なしに使われている
・相手の理解度を確認していない
という“情報の飛び越え”が起きていました。
でも本人にとっては、「それらが抜けている」「これを言わないと相手にとっては話が見えない」という意識がなかったんです。💡 ネイチャースタイル独自の視点
レッスンを通じて感じるのは、言葉足らずの問題は、単なる「説明の技術」だけではないということです。
🧠 頭の中で起こっていること(情報が伝わりにくい理由)
特に、「情報のまとめ方・処理の仕方」に独自のパターンを持つ方は、次に挙げるような感覚が強くなることがあります。・情報を「一つのセット」にしてしまう
頭の中で物事がカチッと整理されると、その情報が非常に明確で完璧な「一つのセット」になります。
そのため、そのセットを相手に渡すときに、「相手が分かるように、一つひとつ細かく分けて渡す」ということをつい忘れてしまいがちです。
・頭の中の「図」や「設計図」が相手にも見えると思い込む
あなたは、話の内容や手順を、頭の中で絵や設計図のように構造化して理解しています。
そのため、相手にもその「図」や「手順」がそのまま見えていると無意識に思ってしまいます。
結果として、図の説明に必要な「最初(前置き)」や「流れ(経過)」、「最終的なゴール(目的)」といった言葉(=図の枠組み)が抜け落ちてしまうのです。思い込みを防ぐ「3ステップ話法」
[心構え] “相手の頭の中”には、自分が話さないと“自分の頭の中”は見えないと意識する。
“相手の中に地図を描く”ように、自分の中だけにある情報を、相手の中にも描くように伝える。1. “前提”を言葉にする習慣をつける
「この話は〇〇の続きです」「前提として△△があります」「こういう意図でこの話をしています」など、背景を一言添えるだけで、相手の理解度が大きく変わります。2.「具体的=優しさ」という新しい定義を持つ
「言葉足らずになっていないか?」と不安になったら、すぐに「誰が、何を、いつやるのか?」という具体的な要素を付け足して話す。
特に主語抜けに気を付ける。3. 相手の理解を確かめる
「ここまでで大丈夫ですか?」「伝わってますか?」と聞くことは、相手への思いやり。
この③が特に大事で、会話の最後に「わかりづらいところなかったですか?」「この説明で伝わってますか?」と一言添えるだけで、思い込みを防げます。ネイチャースタイルのレッスンでも、実際にこうした“前提や確認の練習”を繰り返すことで、会話のズレが減っていく方が多くいらっしゃいます。
💖 カウンセラーからのメンタルアドバイス:自己否定に陥らないために
●言葉足らずに悩む方は、「伝わらない=自分がダメ」と思ってしまう方もいます。
でもそれは違います。
伝わらないのは、あなたの“価値”ではなく、“伝え方のスタイル”の問題です。
認知の違いがあるからこそ、工夫が必要。そしてその工夫は、誰にでもできるものです。●中には、「長く説明すると面倒くさい人と思われそう」「何度も言うのは失礼かも」という不安から、省略してしまう方もいます。
でも実際には、丁寧に補足してくれる人ほど信頼されるのです。教室の受講生さんの中にも、以前は「説明が苦手」とおっしゃっていた方が、「補足を加えたら、職場で“話が分かりやすい人”と言われるようになりました」と嬉しそうに話してくださったことがあります。
🧩 最後に
ネイチャースタイルでは、こうした“認知のズレ”に寄り添いながら、一人ひとりに合った伝え方を一緒に探していきます。
あなたが自信を持って、明確に情報を伝えられるようになるまで、スキルとメンタル両面からサポートいたします。
👉 受講者の声一覧
👉 話し方レッスン成果|受講生インタビュー次回も「話し方のコツ、ワンポイントレッスン」で、日常をもっと心地よくするヒントをお届けします✨
[吉国 裕子] 話し方教室 ネイチャースタイル / コミュニケーショントレーナー・心理カウンセラー
-
- 2025.11.07会話に入れない悩み解消!心理学で解く「蚊帳の外」にならないコツ
-
こんにちは!
話し方教室ネイチャースタイルの吉国です。今回は、「複数人で話しているとき、なかなか会話に入れない」「話題の流れが早くてついていけない」「2人なら話せるのに3人以上になると黙ってしまう…」というお悩みについてお話しします。
実はこの悩み、とても多くの方が感じておられます。当教室でもよくご相談いただきます。
特に、真面目で周囲に気を配れる方ほど、慎重になりすぎて発言のタイミングを逃してしまうんです。
実はこの現象、心理的にも構造的にも“自然なこと”なんです。🗣️ なぜ、会話に入れないと感じるのでしょうか?
複数人の会話では、テンポや雰囲気が一気に変わることがあります。
・話題がどんどん移り変わる
・すぐに次の人が話し始める
・誰が話すかが自然に決まっていくこうした中で、「どのタイミングで話していいのか分からない」「話しても聞いてもらえないかも」と不安になるのは当然です。
🟡具体的には:
1. 「失敗したらどうしよう」という不安:何か発言して、場が白けたり、間違ったことを言ったりするのを恐れる心理です。完璧な発言を求めすぎて、結局何も言えなくなってしまうのです。
2. 「自分の話は面白くないかも」という自己評価の低さ:話のトピックに詳しい人がいると、「自分なんか」と思ってしまい、遠慮してしまうケースです。
3. 情報処理が追いつかない:話題が次々と変わる、誰が話すか予測できない、その中で自分の話をまとめないといけない… これは“会話のマルチタスク”状態。特に真面目で丁寧な方ほど、じっくり考えているうちに話題が変わってしまうことも。実際、当教室の受講生さんの中にも、「頭の中で言いたいことはあるのに、気づくともう次の話題に変わっていた」という方がたくさんいらっしゃいました。
これは、あなたの「協調性の高さ」や「慎重さ」の裏返しでもあります。しかし、そのままだと会話の楽しさから遠ざかってしまいますね。✨ ネイチャースタイル流! まずは「沈黙の質」を変える
当教室では、話す技術だけでなく、「心構え」を大切にしています。
複数での会話で大切なのは、「ずっと話すこと」ではありません。
無理に話そうとするより、「質の高い沈黙」を心がける方が、会話の流れに乗りやすくなります。🟡質の高い沈黙とは:
・話している人にしっかり目を向ける(目力で「聞いていますよ」と伝える)
・適度な相槌(「へえ」「なるほど」「それ面白い!」など)を打つ
・笑顔で時々頷く
・体は話し手に向ける短いリアクションで“共感”を伝えるだけでも、会話に参加している感覚が生まれます。
そして、周囲に「この人も話に関心を持っている」と伝わり、自然と会話に入りやすくなります。実際、受講生のAさんはこの方法で「聞き役から話し手に変われた」と話してくれました。
【受講者様の声から】
「以前は無言でいると『つまらない人』と思われている気がして焦っていました。でも、先生に『まずは聞く姿勢のプロになりましょう』と言われて。笑顔で頷くだけでも、会話に参加できていると実感できました!」(30代・営業職)🚀 実践テクニック!「たった一言」で会話の輪に入る
「そろそろ何か話さないと…」と思ったら、長いスピーチは必要ありません。
当教室で効果を上げている、シンプルな「介入テクニック」を試してみましょう。1.エコーバック・プラス1(オウム返し+質問)
直前の人が話した内容を少しだけ繰り返し、そこから短い質問を投げかけます。これが最も安全で効果的な参加方法です。🟡たとえば…
話し手(相手):「先日キャンプに行ってさ〜」
聞き手:「キャンプ、いいですね! どうでした?」
👍相手の話に関心があることを示し、質問で次の発言を促せる。話のバトンをもらいやすい。2.感情の共有
話題そのものに対する感想や、話をしている人の感情と同じ感情の言葉を、驚くほど短く表現してみましょう。🟡たとえば…
話し手(相手):同僚が仕事の成功談を話している
聞き手:「それはすごい!」「おめでとう!」
👍簡潔に共感を示し、好印象を与える。発言のハードルが低い。
みんな:怒っている
自分:一緒に怒りながら「むかつくー!」
👍気持ちを共有していることを示し、場に溶け込める。3.“話す”より“興味を持つ”
話題に乗れないときは、相手に質問してみましょう。「それってどういうこと?」「最近それにハマってるの?」など、興味を持つ姿勢が会話の入口になります。4.短いコメントから参加する
「○○さんの話で思い出したんですが…」など、前の話題を拾って一言加える練習をします。
無理に新しい話題を出そうとせず、“つなげる発言”を意識するとスムーズです。💖 カウンセラーからのメンタルアドバイス:完璧を求めない勇気を持とう
🟡心理カウンセラーとして、特に伝えたいのは、「発言の完璧さ」を求めるのをやめる勇気。
会話はキャッチボール。あなたが話すことは、誰かにとっての「パス」であり、完璧なホームランである必要はありません。
「話の輪に入れない自分はダメだ」という自己否定のループから抜け出すために、まずは今日、会話中に「相槌を5回打つ」という小さな目標を立ててみてください。
小さな成功体験が、あなたの不安を少しずつ和らげ、自然と発言への意欲につながります。安心感が生まれると、言葉が自然に出やすくなります。
ネイチャースタイルのレッスンでも、「話す前にまず“安心”をつくる」ことを大切にしています。🟡「話せない=ダメ」ではない
会話に入れないとき、自分を責めてしまう方が多いです。でもそれは“場の性質”によるもの。あなたの価値は、話す量では決まりません。
🟡「沈黙も参加の一部」
相づちや笑顔も立派なコミュニケーション。無理に話そうとせず、まずは“その場にいること”を大切にしましょう。🧩最後に
ネイチャースタイルでは、実際の会話場面を想定したロールプレイも行いながら、「どう入れば自然に話せるか」を体で覚えていきます。
「聞き役ばかりになってしまう」「グループになると疲れる」という方も安心してご参加くださいね。次回も「話し方のコツ、ワンポイントレッスン」で、日常をもっと心地よくするヒントをお届けします✨
👉 受講者の声一覧
👉 話し方レッスン成果|受講生インタビュー
[吉国 裕子] 話し方教室 ネイチャースタイル/ コミュニケーショントレーナー・心理カウンセラー